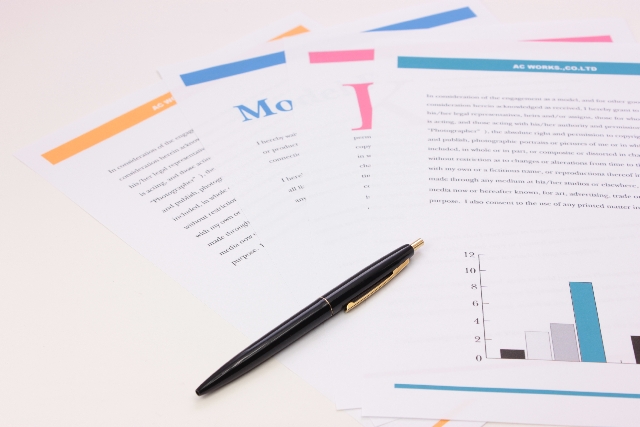


24年の確定申告は必要?
25年の確定申告が必要になり、無事申告できました。その過程であれこれ調べていると…昨年度自分は申告必要なかったのかなと疑問に思い、こちらで相談させてください
。
24年3月31日に退職(12年勤続)
退職所得の源泉徴収票特別徴収票の「所得税法第201条第1項第一号
並びに地方税法第50条の6第1項第1号及び第328条の6第一項第一号適用分」支払金額に60093円とあります。
退職後にもらった24年の源泉徴収票は支払金額639787円、源泉徴収額9950円とあります。
4月からハローワークに通い、失業保険をもらいました。
退職した会社の違う支店で7月末から10月末までアルバイトをし、11月16日から正規パートとして再雇用してもらいました。
そして年末調整、生命保険料控除も提出し、源泉徴収額は0円になっています。
この過程で今更ながら何か申請は必要でしょうか?
宜しくお願いします。
25年の確定申告が必要になり、無事申告できました。その過程であれこれ調べていると…昨年度自分は申告必要なかったのかなと疑問に思い、こちらで相談させてください
。
24年3月31日に退職(12年勤続)
退職所得の源泉徴収票特別徴収票の「所得税法第201条第1項第一号
並びに地方税法第50条の6第1項第1号及び第328条の6第一項第一号適用分」支払金額に60093円とあります。
退職後にもらった24年の源泉徴収票は支払金額639787円、源泉徴収額9950円とあります。
4月からハローワークに通い、失業保険をもらいました。
退職した会社の違う支店で7月末から10月末までアルバイトをし、11月16日から正規パートとして再雇用してもらいました。
そして年末調整、生命保険料控除も提出し、源泉徴収額は0円になっています。
この過程で今更ながら何か申請は必要でしょうか?
宜しくお願いします。
退職所得は、給与所得の計算とは別にして計算する分離課税です。
主様の平成24年分の収入は
①3月末に退職した前の会社の源泉徴収票・・・課税
②失業保険・・・非課税
③アルバイト収入・・・課税
④正規パート収入・・・課税
⑤退職所得・・・分離課税
⑤の退職所得は「所得税法第201条第1項第一号」ですので、税金の精算が済んでいます。
①、③、④を合算して年末調整されていれば、確定申告不要です。
正規パートの源泉徴収票(年調済み)で①の分が加算されていればOKですが
加算されていない、かつ①③④の合計が103万超えるのであれば、確定申告必要です。
主様の平成24年分の収入は
①3月末に退職した前の会社の源泉徴収票・・・課税
②失業保険・・・非課税
③アルバイト収入・・・課税
④正規パート収入・・・課税
⑤退職所得・・・分離課税
⑤の退職所得は「所得税法第201条第1項第一号」ですので、税金の精算が済んでいます。
①、③、④を合算して年末調整されていれば、確定申告不要です。
正規パートの源泉徴収票(年調済み)で①の分が加算されていればOKですが
加算されていない、かつ①③④の合計が103万超えるのであれば、確定申告必要です。
理学療法士1年目のものです。現在、九州の介護老人保健施設にて理学療法士として働かせていただいておりますが、来年度東京の彼と結婚を控えており、
転職したいと考えております。
東京の理学療法士は飽和状態なのですか?九州より需要はありますか?
私は介護老人保健施設で理学療法士として働きたいですが、回復期の方が需要ありますか?
回答よろしくお願いいたします。
転職したいと考えております。
東京の理学療法士は飽和状態なのですか?九州より需要はありますか?
私は介護老人保健施設で理学療法士として働きたいですが、回復期の方が需要ありますか?
回答よろしくお願いいたします。
通所リハビリじゃだめですか?1番PTの需要多いと思いますけど。他は人員配置要件の関係上、あまり雇用機会は期待できないでしょうね。質問者さんの東京では?ははっきり解りません。ハローワークのHPで地道に探すしかないかも知れませんね。
4月に退職をした者(24歳)です。
6月から職業訓練を受けることになっているので、収入が少なく年金を払う余裕がありません。
ハローワークに行ったときに、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」というものをもらいました。
免除と「若年者納付猶予制度」では、どちらの方が良いのでしょうか?
6月から職業訓練を受けることになっているので、収入が少なく年金を払う余裕がありません。
ハローワークに行ったときに、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」というものをもらいました。
免除と「若年者納付猶予制度」では、どちらの方が良いのでしょうか?
若年者納付猶予は文字通り保険料の納付を猶予される制度です。
ただし免除認定から10年以内に追納しないと
受給時の年金額に反映しません。
免除の種類には全額免除と半額免除があり
(18年7月からは3分の1納付と4分の3納付制度が加わります。)
全額免除の場合は免除期間の年金額が3分の1に
半額免除では3分の2になります。
これは3分の1を国が負担しているためです。
これだけ見ると免除の方が良く思えますが
免除や猶予の審査は前年度の所得が対象になります。
免除は申請者本人のほか、配偶者と世帯主の所得も審査の対象になります。
(納付猶予は本人と配偶者のみ対象)
免除の場合、本人に所得がなくても
世帯主にある程度の所得があれば承認されません。
一人暮らしで本人が世帯主ならば免除の方が良いと思いますが
親と同居で世帯主や配偶者に所得があるなら免除は承認されません。
ご自分の状況で申請してください。
ただし免除認定から10年以内に追納しないと
受給時の年金額に反映しません。
免除の種類には全額免除と半額免除があり
(18年7月からは3分の1納付と4分の3納付制度が加わります。)
全額免除の場合は免除期間の年金額が3分の1に
半額免除では3分の2になります。
これは3分の1を国が負担しているためです。
これだけ見ると免除の方が良く思えますが
免除や猶予の審査は前年度の所得が対象になります。
免除は申請者本人のほか、配偶者と世帯主の所得も審査の対象になります。
(納付猶予は本人と配偶者のみ対象)
免除の場合、本人に所得がなくても
世帯主にある程度の所得があれば承認されません。
一人暮らしで本人が世帯主ならば免除の方が良いと思いますが
親と同居で世帯主や配偶者に所得があるなら免除は承認されません。
ご自分の状況で申請してください。
関連する情報